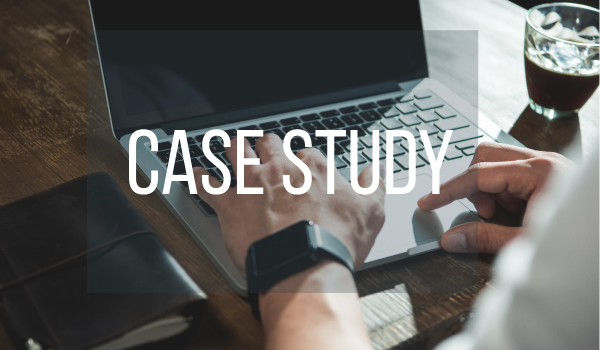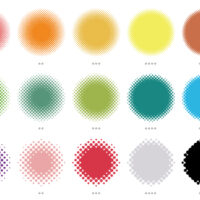ようこそ! Taurus🐂の橋梁点検ノートへ。
再劣化シリーズでは、
読者の皆さまから頂いた質問を改編し、ケーススタディ形式でお届けしています。
「こんな損傷あるんだ」
「だから再劣化するんだ」
「こういう考えもあるんだ」
このブログの記事が、
橋梁メンテナンスに携わる ”あなたの力” になれたら嬉しいです。
ではさっそく、いってみましょう!
※様々なご意見があると思いますが、どうぞ温かい気持ちで読んでいただけると助かります。
ーーーーーーーーーーーーーーー
目次
【再劣化case02:埋設型伸縮装置部の路面陥没】
■質問:埋設型伸縮装置部の路面陥没について
『埋設型の埋設伸縮装置でよく穴があきます。
ひびわれは可動側のみだけです。
補修するときは、加熱合材でしっかり転圧しています。
どうしてすぐ穴があくんですか?
いい補修の仕方はありませんか?
ちなみに補修した時に細長くて薄い鉄板がありました。』
伸縮装置ってたくさん種類ありますよね(^-^;
構造別、材料別、機能別・・・
開発メーカーもたくさんあるので、その種類の多さは想像以上。
では、
伸縮装置の概要ですが、
構造別には以下の3種類。
1.荷重支持型
2.突合せ型
3.埋設型
機能別には 以下の2種類。
1.伸縮吸収型(特殊合材、特殊合成樹脂、特殊合材+鋼製EXP)
2.伸縮分散型(特殊合材+アスファルト)
ちなみに、
今回の質問にあるのは、「埋設型・伸縮吸収型」です。
どうですか?
これだけでもすごい種類になりそうですよね(^-^;
ひと口に「埋設型伸縮装置」といっても、
このようにたくさん種類があるので、その耐久性や劣化機構、補修方法もさまざまです。
伸縮装置について ネットで伸縮装置について検索すると、これまた色々な情報で溢れていますが、わかりやすい資料の1つとしてこはこちら。 「伸縮装置設計の手引き2010年3月 日本道路ジョイント協会 http://joint.ecnet.jp/pdf/tebiki0914.pdf」
ーーーーーーーーーーーーーーー
■Case Study: 一緒に考えてみましょう!
■質問
『埋設型の埋設伸縮装置でよく穴があきます。
ひびわれは可動側のみだけです。
補修するときは、加熱合材でしっかり転圧しています。
どうしてすぐ穴があくんですか?
いい補修の仕方はありませんか?
ちなみに補修した時に細長くて薄い鉄板がありました。』
わたしは下記のように推定していきました(゜-゜)
⇩ ⇩ ⇩ ⇩ ⇩
今回の劣化を繰り返している埋設型伸縮装置の特徴を整理すると、
1.特殊合材を使用した埋設型
2.構成部材は簡素な鉄板くらいしかなく、内部には金網や鋼製伸縮装置はないみたい。
3.可動側でひび割れが入っており、補修した箇所がすぐはがれる。
構成部材が特殊合材と簡素な鉄板ということは、○○〇社等の製品かな?
金網やハニカム構造の部材、突合せ型のEXP(エキスパンションの略)は入っていない。
過去の補修過程で撤去した可能性はあるけど、とりあえずその情報はない。
埋設型の伸縮装置は、伸縮量が比較的少ない小中規模の橋梁に採用されるもの。
使用されている特殊合材というのは、それほど伸縮性に優れている材料ではないから、設計時に想定した伸縮量を超えるとすぐひび割れてしまう。
今回の質問にも可動側でひび割れが入っているということだったし、伸縮量を吸収できていないのでは。
設計時の想定以上に桁の伸び縮みがあるのか、回転してしまっているのか。
これらから考えられるのは・・・・・(゜-゜)
ーーーーーーーーーーーーーーー
■回答: 路面陥没の原因と補修について
埋設型伸縮装置は、段差がないので伸縮装置の通過時の衝撃もなく走行も静かです。
耐久性や施工性にも優れ、適用条件や施工に問題なければ良いこと尽くしの部材です。
しかし、
適用条件や施工等が適切であったとしても、どうしても劣化はしていくもの。
今回のように、ひび割れや陥没が起きてしまうことがあります。・・・
では、どうしたらいいの?( ゚Д゚)
はい。
これからが、今回の大事なところです。
劣化課程を簡単にいうと、
・ひび割れから浸入した水や輪荷重などによって、特殊合材じたいが劣化します。
⇩
・シートやゴム板、鉄板が劣化したり、ずれたり、がたつきます。
⇩
・コンクリート表面が劣化します。積雪寒冷地であれば凍害でガタガタに。
この状態では、いくら強固な補修材で上面のみ補修してもすぐ再劣化してしまいます。
<参考:補修方法>
そのため、
伸縮装置の補修を長持ちするためには、根本原因である下地も同時に補修する必要があります。
どこまで補修費用をかけられるかにもよりますが、
走行性の回復を目的とし、
なおかつ、伸縮装置からの橋面水浸入による桁下への影響がそれほどない場合は、
簡単です。
以下の2つに気を付けて補修します
・下地となる劣化部(コンクリート、シート、ゴム板、鉄板等)をすべて撤去
・補修範囲はなるべく大きく(補修近くにひび割れがあるとそこが弱点に)
できれば劣化したコンクリートの不陸調整を行い、鉄板等を再設置してあげられれば一番いいのですが、部分的に劣化することが多いので、現実的にここまで措置を行うのはできません。
大事なことは下地となる部位が上下動(ずれ)しないようにしてあげることです。
わたしもかなり埋設型伸縮装置の劣化調査に立ち会いましたが、たいだい悪さをしているのは「機能損失した構成部材」です。
撤去してしまえば済むことが多いのですが、補修業者さんに聞くと『構成部材であるシート等を補修時に撤去するのはかなり抵抗がある』とのこと。
機能が損失した部材を残しつづけるのか、
再劣化しないように部材を撤去するのか、
わたしは後者だと思いますが。
と、
いうことで!
・補修材の下地となる合材や鉄板が機能損失しているので、補修部の再劣化が発生する。
・補修方法は、下地の処理(機能損失している部材の撤去、清掃)を行ったうえでアスファルトで補修する。
いかがでしょう?
あなたはどう考えますか?(´-`*)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【さいごに】
伸縮装置は、いろいろなメーカーで開発されていて多種多様です。
わたしもまだ経験したことのない製品がたくさんあります。
すべての製品を知るのは不可能に近いと思いますが、
劣化機構も製品によって特長はあるものの、補修する際に大事なことはそれほど変わりません。
伸縮装置に限らず、
補修するときに大切なことは「補修目的」を明確にすることです。
漏水なのか?
段差なのか?
など
補修=新品同様に補修でなくてもいいのです。
例えば、伸縮装置から漏水している=新品と交換であれば
お金がかかり過ぎてしまいます。
診断結果の健全度評価は、
「交換」が目的ではなく、「止水」のはずです。
それであれば、
ホームセンターで市販しているコーキング材でもいいのです。
目的や優先順位に応じて、健全度の回復程度や補修方法を決定しましょう。
ただ、これが難しいんですよね。
よく言われます。
『言うは易し』、です。
このブログがその解決策の1つになればと思って運営しています。
今回は埋設型伸縮装置の再劣化事例ですが、次回は鋼製伸縮装置について書いていきたいと思います!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■お問い合わせについて■
橋梁点検でわからないことや不安なことありませんか?
「こんな損傷があったらどうすれば?」「ほかではどう対応しているの?」「この記事の意味をもう少し知りたい」など。
どうぞ気軽な気持ちでお声がけくださいね!
ブログへのご意見・ご要望につきましては、下記専用フォームからお寄せください(´-`)
CONTACT | 【Linxxx公式】現場で役立つ橋梁点検ノート